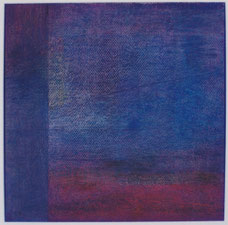『自由工房』を応援してくださったコンテンポラリー・マガジン『The Earth』を発行していた忽那修徳氏から巻頭の「ジ・アース/トーク」を依頼され執筆しました。忽那氏の愛媛での取組みに感心し、出会いを大変喜んでいました。
テーマ 《最近「このまま続けているとヤバイ」と思ったことは?》
「人間死んだ気になれば何だってやれっるさ」どうにもありふれたフレーズだが、なぜかしぶとく頭の隅にこびりついていて、時々口のなかでつぶやいてみることがあった。死を秤にかけるほどのどれほどの苦境があったのか、過ぎ去った痛みはもう量りようもないのだが、なにしろ、死そのものについての恐怖感が人一倍強かったのだから、これはまったく意味のない言葉で、ほとんど役にはたたなかった。少年期から異常なはど死を意識していた。深夜いわれのない恐怖と虚脱感にのみこまれて、身体を縮め、息をつめて耐えていた記憶を鮮明に残っている。いまもすっかり消え去ったわけではないが、あのどうしようもない、心細いうつろな感触は、次第に間が遠くなり、うすれていった。(きょう、ママンが死んだ-)で始まる、カミュの「異邦人」を初めて読んだのは、戦後しばらくしてのことだから、たぶん二十五、六才の頃だったろう。二十世紀ヨ-ロッパの暗さの反映ともいわれる、人間の不条理を鋭く描いたこの小説との出会いは、まったく衝撃的だった。ママンの死、アラビア人の死、死刑囚ムルソーと続くこの悲劇的な物語は、処刑を待つムルソ-が、はじめて、世界の優しい無関心に、心をひらいて終るのだが、かつて、そしてその後も、小説の主人公にこれほどの一体感を抱いたことはないし、またこれほど確かな人間の実在を信じさせられたこともない。以来「異邦人」は僕にとって心の指標であり、同時に、仕事の方向を選ぶための大切な基盤だとも考えてきた。それはまた、いやおうなく青年期の死の認識を形づくる力ともなったようだ。
去年かけがえのない友人を二人も失った。今年になって、五月には母の死を看取り、六月には身近な人の死が相ついだ。しばらく遠ざかっていた死の意識は、こんな風にして、またあらたな表情で現われてきたわけだが、いまそのきびしい相貌を前にして、うろたえている。カミュは「異邦人」の自序のなかで書いている。「生活を混乱させないために、われわれは毎日嘘をつく」と。「嘘をつくという意味は、無いことをいうだけでなく、あること以上のことをいったり、感じる以上のことをいったりすることだ」とも。死の恐怖より、生きることに馴れた怖さがある。このままじゃ、ヤバイ。
1993年7月25日 The Earth ジ・アースVOL.28 ジ・アース/トーク